『カンヌで勝つための「勇気・根気・侠気」、プロデュース視点でカンヌを分析』2014年8月26日開催 月例セミナー 第3部 イベント報告
- 掲載日:2014年12月3日(水)
Web広告研究会による「3つの視点によるカンヌ報告会 ~普遍視点・デジタルネイティブ視点・プロデュース視点」第三部は、プロデュース視点をテーマに、長年にわたりカンヌの現場を取材してきた銀河ライターの河尻 亨一が、カンヌ受賞作を生みだすために必要な、「勇気・根気・侠気」を示した。
カンヌ受賞作が生まれやすい環境とは
まず河尻氏は、講演テーマのプロデュース視点を「受賞作が生まれやすい環境を作るには」とし、カンヌ受賞作品から知識を得るだけでなく、より踏み込んだ、カンヌを獲るような作品にかかわるとしたら、どのように自身がプロデュースするのか考えてもらいたいと話した。
そのなかで挙げられたキーワードが、「勇気」「根気」「侠気」の3つだ。
「プロデュース視点というと雲をつかむような言葉ですが、もう一歩踏み込んで、現実的に無理だとしても、今日は一度、“自分ごと”としてプロデュースしてみるには?、というアングルからお話したいと思います。
ただし、実際にはそれぞれの方が所属する会社、部署や立場で変わってきます。一概にこれが正しいとは言えないのですが、みんなに共通するものは、結局“勇気や根気、侠気”といったマインド面の事柄なのではないでしょうか。
なぜなら、日本の広告はこういった場所でもっと評価されるポテンシャルがあると感じているからです。受賞作をシルバーやブロンズまで見ていくと、割とだれでも思いつくだろうという作品もあり、実際に受賞したいという意欲があるかどうかというのが、すごく大きい。カンヌからは「やってみた」精神のようなものを感じるのですね。カンヌは未来の広告を試行錯誤する場でもあります。
もちろん、国内でワークする施策とグローバルな広告祭で評価される作品的な企画には違いもあり、受賞者にはリスペクトの感情が湧くとはいえ、一概に賞を穫りさえすれば偉いというものでもありません。しかし、成長中の元気な企業ほどチャレンジングなキャンペーンをぶつけてくる傾向はあり、カンヌはその国の広告産業力や企業コミュニケーション力も試される“W杯”のような側面もありますから、現状ではもったいないというふうにも私は感じています。正直『日本はもっと勝てるはずだ』と思うのですが、現地に行くと、これだけの経済規模の国のわりに、全体として『おとなしい』印象があるのは事実です」
もちろん、グランプリやゴールド受賞作品には「いったいどうしたらできるのか?」という、スケールの大きな作品が多い。しかし、約1000の受賞作を見ていくと、だれでも思いつくようなアイデアもある。大きな違いは、実際にやりきれるかどうかだというのだ。
また、審査終了後の日本審査員にインタビューし続けてきたという河尻氏は、日本の受賞作が多い年、少ない年にかかわらず多くの審査員が「広告主が変わらないと」と語っていたことを述べる。いろいろな事例を見るとわかるように、根本の発想が違うというのだ。どれだけ骨太のアイデアを作れるかというアイデア勝負であり、失敗する可能性もあるなか「勇気・根気・侠気」でぶつかり、グローバルで鎬を削り合うのがカンヌの世界だという。
「デザイン部門など、クラフトのすばらしさが評価されるカテゴリーでは日本勢は圧倒的な強さを見せます。ディティールへのこだわりと印刷技術の高さは他国を凌駕している面があります。ところが、それ以外のフィルム、プロモーション、PR、ダイレクト、チタニウム、ブランデッドコンテンツ部門などではそれほど強くない。ネット広告を評価するサイバー部門は、かつてはサイトの作り込みの凄まじさなどから日本は高く評価されていましたが、いまや『ネット広告=統合キャンペーンの中心』というふうに時代がスライドしてきました。こうなるとやっぱりアイデア勝負です。
だからといって、日本人はアイデアが出せないわけではないと思っています。シャープで革新的な企画を考えられる人材、それを形にできる人材はいると思うのですが、その羽を十分に羽ばたかせる機会は十分にはないというか…。“賭ける”チャンスが少ないように思うのですね。いまの日本の経済状況にもちょっと似ています。『勇気・根気・侠気』などという古めかしい言葉をあえて使うのも、この閉鎖感を突破するにはどうすればいいのか? という意図があります」
ソーシャルメディアはあって当たり前
カンヌを取材するだけなく、実際にエントリーもしているという河尻氏は、核となる部分の99%はこれまでの話で語ったとしたうえで、第一部と第二部の講演を補完する形で、残り1%である2つのポイントを紹介した。
1つ目のポイントは、「ソーシャルメディアはインフラ」として、基本的には目に見えないモノになっているということだ。
「ソーシャルメディアはもう古いと思わせるぐらい、当たり前になっています。少し前、たとえば2009年はオバマ大統領選がグランプリを獲り、2008年ごろにFacebookやTwitterでてくると、Facebookのフレンド数を減らすとタダになるバーガーキングのキャンペーンなど、仕組みに合致した企画が賞を獲っていたし、ベストバイのTwelpforceのような、お客様サービスをTwitterの仕組みを丸々使ってやったアイデアがクールとされていました。いわば水道管やガス管といったインフラそのもののユニークな活用法を評価していました。それらを使っているだけで『スゴい』みたいな風潮さえあったのです。
しかし、今は生活に必要なモノ、つまり“広告必需品”となっており、今年はソーシャル的な広がりをデフォルトとしてふまえて企画された映像コンテンツの受賞が目立ちました。トーンとしては素人的でありながらプロでないと作れない、その方程式の解がどこにあるのか? を競い合っているという印象です。個人的には、ウェアラブルのマーケティング活用事例などが『今年こそ来るか?』という事前予想をしていたのですが、ふたを開けるとそうではありませんでした」
一方、世界からすると日本のSNS利用率は66%で最低だという「SNSの利用度で日本は49ヵ国(地域)中最下位」(カンター・ジャパン調査)を河尻氏は紹介した。
調査によると、SNS利用率の1位はインドネシア(98.5%)で、インターネットがあるのだろうかというイメージの国でも90%を超えており、そういった世界から作品が集まる舞台で戦うのがカンヌであり、「 グランプリのVolvo『Epic Split』など、『どうすればユーザーがソーシャル上でシェアしたい気持ちになるか?』を考え抜いた企画だと思います」と河尻氏は説明した。
ソーシャルグッドのブームが続く
2つ目のポイントは、「ソーシャルグッドは定着した」というものだ。
「3年ぐらい前から言われだしたソーシャルグッド。私はこの手のものは一時の流行りかと思っていたのですが、広告のアプローチとして定着しつつあるようです。さきほどハイジさんが紹介したFuture Lionsの企画などは、ほとんどがソーシャルグッドの範疇に入ります。それぐらい、若い世代の心をつかんでいる。詳しくは私が執筆したこちらの記事をお読みいただけるとうれしいのですが(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40268)、私はこれは『21世紀型のブランディング』だと思っており、必ずしも『社会貢献』という日本語の枠だけにはおさまらないものとして考える必要があると思います。それは企業の成長のエンジンにもなりうるコミュニケーション戦略です」
実際、河尻氏が個人的にまとめたという「Cannes Lions 2014 Best 100(http://www.youtube.com/playlist?list=PLh926eoEx9nA__lpXtU2ENuDdAy1_oZzb)」の記事では、紹介する作品のバランスに気をつかったにもかかわらず、100作品中の約40作品をソーシャルグッド系が占めたという。2013年のPR部門では、ゴールド6作品がソーシャルグッド系になるほどの一大ムーブメントで、この流れは2014年も踏襲されていたことから、2010年代はソーシャルグッドがプロデュースのツボになってくるのではないかと、河尻氏は話した。
また、2つのポイントは別々ではなく、「ソーシャルメディアのインフラ」と「ソーシャルグッドの定着」を掛け合わせて考えることが重要だという。
「人と交流するためのツールとしてのソーシャルと、社会というソーシャルはつながっていて、そこを見る必要があるでしょう。そうすると、マーケティングや今の時代の見通しがすごく良くなっていく。その感覚でアイスバケツチャレンジなどを見ると、なぜこれだけ拡散しているのか理由がわかると思います。自発的に集まったものだとはいえ、きちんと2つの文脈を押さえた掛け算の企画になっています」
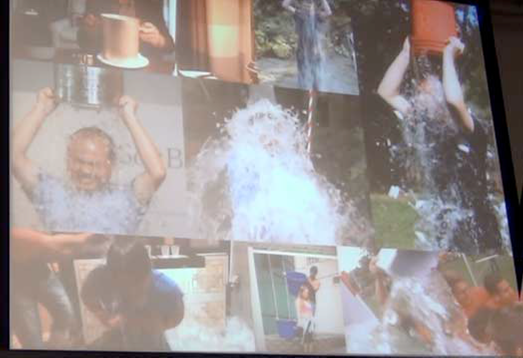
アイスバケツチャレンジ
Facebookで広がった、ALS(筋萎縮性側索硬化症)支援のアイスバケツチャレンジを例にとると、水をかぶるというだれでも簡単にできる「人間的・体験的・生理的」な体験のアイデアがあり、それを3人が指名するという仕組みが掛け合わされている。これはソーシャルメディアに非常にマッチした企画で、事実、ALS協会の2014年7月の寄付金は、過去の同時期と比べて約400倍の成果を達成したという。
「今バズる施策というのは、だいたい掛け算のプロデュースができています。同時に気をつけなければいけないのが、文脈を読むこと。企業がマーケティングの目的を丸出しにして、仲間だという顔つきで参加すると炎上すること。ソーシャルメディアはフラットな世界なわけですから、そこに参入する以上はユーザーからすれば“同列”なわけです。実際には違うのですが、大人な態度で友達になろうとしないとコミュニケーションが成立しません。
コワいのはブランド崩壊です。ソーシャル環境では、ネガティブ、キャッチー、センセーショナルなコンテンツは瞬く間にスゴい数の人にシェアされるため、良いことをやってきたブランドが、一夜にして悪人になってしまうケースさえある。一個人のこととして考えれば当たり前なのですが、ごり押しは嫌われますよね? ユーザーとのコミュニケーションに対して真摯に本気でやる必要があります」
ソーシャルグッド流行の背景には、従来の4マス媒体が昔ほど力を持たなくなったことも大きいという。従来メディアだけでは、ファン層をカバーすることが難しくなっているため、それに代わるコミュニティプラットフォームを使って、より深いファンになってもらうというのだ。ソーシャルグッドとは、言い換えると「自社カスタマーコミュニティグッド」であると河尻氏は話した。
また、先進国における公共サービスの疲弊も理由の1つ。「将来、成り立たなくなるだろう公共サービスをだれが代わりに担うのか? NPOなど非営利組織や地域コミュニティなどへの期待があるが、豊富な資金があるわけではない。その部分を企業がある程度、担わざるを得ない状況になってきている部分があり、そういった社会還元事業は企業の持続的成長と実は相反しないように思うのです。広告には社会へのサービスといった役割もあり、デジタル化の進展でそれは必ずしも面白いコンテンツの提供という範囲に留まりません」と河尻氏は述べる。加えて、富裕層と貧困層の格差社会化問題もあるという。
公共サービスの疲弊や格差社会化が進むなか、力を持っている組織、つまり企業が手を貸していく必要性がでてくることからも、ソーシャルグッドのブームができているという河尻氏は、「だからこそ、ソーシャルメディアやソーシャルグッドの流行は1~2年で終わらない。むしろグローバル企業はこれまで以上に“そこ”を取りにくる可能性さえあると思います。彼らはメディアのレイヤーではなく、コミュニティのレイヤーでカスタマーを囲うことを広告手法として洗練させているのではないでしょうか?」と分析した。
第二部で紹介された、英会話スクールと高齢者をつないだ「Speaking Exchange」などは、企業の事業目的と、高齢者をサポートするという社改善の目的にブレがなく、ソーシャルグッドの好例だ。アイデアはシンプルだが、目的が一致した事例であり、現在もプロジェクトは進行している。「英会話教室の特色をメディア訴求するのではなく、コミュニティ構築のプロセスで体験してもらおうという発想が根底にある」という。
世界で見つけた2014年版カンヌ厳選事例集
講演の後半は、第一部と第二部で紹介された作品とは別に、河尻氏が厳選した注目作品が紹介された。
GayTMS

オーストラリア、メルボルンで行われたゲイ・レズビアンの感謝祭に合わせた銀行のキャンペーン。協賛8年目を記念して、ATMをすべて「GAYTM」にするという単純なアイデアだが、「本当にやったということがすごい。これはみんなが喜んで、ソーシャルで爆発します。まさに勇気と侠気ですね。感謝祭をずっとサポートし続けている根気もすごい」と河尻氏は評した。また、手数料を365日、チャリティーとしてコミュニティに還元し続けるという仕組みになっているのもポイントだ。
Samsung Maestros Academy

サムスンがイタリアで行ったキャンペーン。伝統工芸の職人育成に悩む山村と、失業率が高いにもかかわらずスマホばかり触っているイタリアの若者を、デジタルデバイスで結びつけて解決しようという、ソーシャルグッド的な事例だ。デジタルデバイスを使って職人が生徒を助け、いろいろな体験や学習ができるようにしている。
「学ぶプロセスがディスカバーチャンネルで12話のドキュメンタリー番組になり、PRコンテンツとしての出口もきっちり計算されています。大きな意味で社会にも貢献していく。これを一度やってしまうと、3か月のキャンペーンで終わりというのはなかなかうまくいかなくて、じっくりと本当の職人を育てていくという根気の部分が試されてます。」
SWEETIE

「非営利組織の最も過激なキャンペーン。広告の発想とは違う、本当にマーケティングに入ってくるのかという感じがしつつも、ショッキング過ぎて話題になっていた」と河尻氏が紹介したのは、オランダの人権団体のキャンペーン。
世界的に増えているWebカメラを使った児童性犯罪を防ぐため、SWEETIEという人間そっくりのアバターを作り、おとり捜査をするというものだ。実際に逮捕者もでており、多くのニュースメディアが取り上げるなど、人々に性犯罪の問題を告知した。
The Impossible Family Portrait

こちらは、ファミリーブランディングと位置付けられたスカイプのキャンペーン。出稼ぎに来ている男性に、遠く離れた家族との思い出の写真を提供するため、スカイプを使って壁一面に家族を映し出し、家族写真をプロカメラマンが撮るというものだ。
「さまざまなシリーズがあり、スカイプが人間性のあるツールのように感じられて共感性が高く、デジタルサービスの冷たいイメージとは違った見え方をしてくる。架空の感動ストーリーをこしらえているわけではなく、こういった施策もトレンド的にはソーシャルグッドの流れにハマります。ソーシャルブランディングというのはこういうことなのかな?と思います」
First Kiss

一億近くYouTubeで再生されている、米国西海岸系のアパレルブランド「Wren」のキャンペーン。初めて出会った2人がキスをするというドキュメンタリー映像だが、登場人物はモデルや歌手などが多く、オーディションで選んでいるという。
「これを企画した女性演出家は、社長にアイデアを直接持ち込んだそうです。あまり予算がないなかで始めたら、すごいことになっていて、ちょっとあり得ないぐらいのドキュメンタリー。ただし、本当の素人が出演者だと、ちょっとイタい感じになってしまいそうというか、これは成立しにくいんじゃないでしょうか」
本気でやりきれるか
河尻氏は講演の終わり、カンヌで叫ばれている「Authentic」というキーワードを紹介。Authenticを直訳すれば「本物の」となるが、川尻氏はこれを「本気」という意味ではないかと話した。
「300近くあるカンヌセミナーでは、〆にAuthenticというワードが頻繁に使われています。辞書的には、『本物の~、正真正銘の~』といった意味の言葉ですが、発信側のマインドとしては『本気の~』というふうに解釈してもよいのではないかと思います。
今日、お見せした事例群は、通常の施策と比較すると“クレイジー”に思えるものが多いです。しかし、クリエイティブのフィールドではそれは褒め言葉です。それぐらい本気でやるということが世界で勝つためには必要で、『勇気、根気、侠気』というキーワードも、そこから発想しました」
その他、2014年のカンヌでは、「ネイティブアド」や「キュレーション」の注目度も高かったという。「特に海外のプレス関係者・ジャーナリストたちの関心が高く、バックステージの囲みインタビューでは、そういった質問がしょっちゅう飛び出していました。2010年以降のトライアルが世界的に一段落し、ネットでウケるコンテンツを制作するための方法論もかなり確立してきたので、次フェーズとして情報の効果的な流通や新しい広告ビジネスモデルに興味が移りつつあるのではないでしょうか?」とのこと。女性の審査委員長と審査員の比率が増えていることも変化の1つだ。セミナーに関しても、マリッサ・メイヤー(米Yahoo! CEO)、シェリル・サンドバーグ(Facebook COO)などの、女性リーダーが招かれていたという。
また、今後は業態別に部門が設けられるのではないかと、河尻氏は次のように話した。
「以前のカンヌは、テレビ、ラジオといったメディア別に賞のカテゴリーが分かれていました。そこに、プロモーションやダイレクトといった手法別のカテゴリーが新設されていきましたが、こうなると重複受賞が多すぎてよくわからないことになっている面もあります。こういった課題を解決するには、業態別にする方向が考えられると思います。今年始まったヘルスケア・ライオンというのも、そういった試みだと解釈すると腑に落ちます。
ある審査員に話をうかがったところ、『世界的にヘルスケア業界は、治療から予防へと言われているが、実際にはそれほどうまくシフトできていない。多くの先進国が高齢化していく中、このままだと各国の医療費が大変なことになってしまう可能性もあるわけです。そういった課題を抱える業界の産業構造そのもののリ・デザインにも広告の力が生かせるのでは? というのがヘルスケア・ライオンの狙いなのかもしれません』と語っていました。カンヌを何年も見ていると、“広告”という言葉の意味やポジションも、いよいよ変わって来たと思わざるをえませんね」

